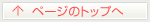2012年10月:第3回 日本声楽コンクール(旧 日本歌曲コンクール)
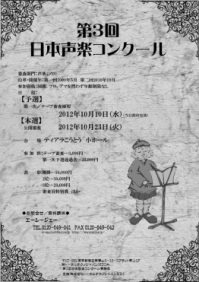
| 審査部門 | 声楽 |
| 参加資格 | 国籍、プロ、アマを問わず、年齢制限なし |
| 日程 | ●予選 第一次/テープ審査締切 2012年10月10日(水) ●本選 公開審査 : 2012年10月23日(火) |
| 会場 | ティアラこうとう小ホール(東京都江東区住吉) |
受賞者は以下のとおりです(五十音順、敬称略)
- 優 勝
- 該当者なし
- 第2位
- 田中深春(国立音楽大学音楽部声楽科卒)
オペラ「ランメルモールのルチア」より“Regnava nel silenzo”/ドニゼッティ
- 第3位
- 溝呂木さゆり(フェリス女子学院大学院卒)
オペラ「夕鶴」より“与ひょう 私の大事な与ひょう”/團伊玖磨
- 入 賞
- 山田悦子(東京順心女子短期大学 音楽科ピアノ専攻卒)
Musica proivita/Stanislao Gastaldon
- 審査員家永勝特別賞
- 中西千絵(奈良文化女子短期大学 音楽学部声楽科卒)
オペラ「ロメオとジュリエット」より“ああ幾度か”/ベッリーニ
- 審査員家永勝特別賞
- 松木美智子(杉野女子短期大学 生活芸術科卒)
オペラ「ラ・ボエーム」より“私の名はミミ”/プッチーニ
2010年10月:第2回 日本歌曲コンクール
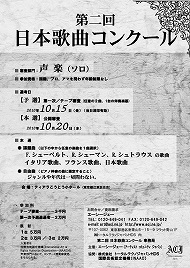
| 審査部門 | 声楽(ソロ) |
| 参加資格 | 国籍、プロ、アマを問わず、年齢制限なし |
| 日程 | ●予選 第一次/テープ審査締切 2010年10月15日(金) (任意の2曲、1台の伴奏楽器) ●本選 公開審査 : 2010年10月20日(水) |
| 本選課題曲 | ●課題曲(以下の中から任意の楽曲を1曲選択) F.シューベルト、R.シューマン、R.シュトラウスの歌曲イタリア歌曲、フランス歌曲、日本歌曲 ●自由曲(ピアノ伴奏の曲に限定すること)ジャンルや年代は一切問わない。 |
| 会場 | ティアラこうとう小ホール(東京都江東区住吉) |
| 参加料 | テープ審査 3,000円 / 第一次予選通過者 20,000円 |
※入賞者は、国際芸術認定機構(International Art & Rights Authorize Organization-INNAO)の声楽部門において、コンサート演奏家資格を与えられる。
受賞者は以下のとおりです(五十音順、敬称略)
- 優 勝
- 該当者なし
- 第2位
- 該当者なし
- 第3位
- 冨澤 克子 / 間山 るみ子
- 入 賞
- 伊藤 雅俊
- 家永勝特別賞
- 間山 るみ子
2009年05月:第1回 日本歌曲コンクール
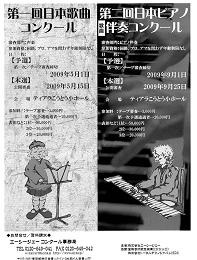
| 審査部門 | 声楽 |
| 参加資格 | 国籍、プロ、アマを問わず、年齢制限なし |
| 日程 | ●予選 第一次予選/テープ審査締切 2009年5月1日(金) ●本選 公開審査 : 2009年5月15日(金) |
| 会場 | ティアラこうとう小ホール(東京都江東区住吉) |
| 参加料 | テープ審査 3,000円 / 第一次予選通過者 20,000円 |
※上位入賞者は、国際芸術認定機構(INNAO)の声楽部門において、コンサート演奏家資格を有することができる。
受賞者は以下のとおりです(五十音順、敬称略)
- 優 勝
- 木村 善明
- 第2位
- 西野 郁子
- 第3位
- 浅井 美波
- 審査員特別賞
- 山中 瑠璃子
第一回 日本歌曲コンクールにつきまして
このたび第一回日本歌曲コンクールを開催しました。このコンクールは歌曲に特化したものですが、30人を超える方が第一次審査にエントリーされ、14人が最終選考に臨まれました。思った以上に非常に高いレベルでの決勝戦になり、コンクール事務局としても驚きを隠せませんでした。そして、審査も非常に難航し、最終的に順位は決定しましたが、当日の選曲によっては、順位が入れ替わることも十分に考えられ、ほとんど差がなかったと感じております。
今回のコンクールは国内限定のコンクールでしたが、国際コンクールの入賞者に匹敵する、世界的にも活躍できる逸材が受賞していることを、強く感じました。彼らが楽壇に新風を吹き込む日が今から楽しみでなりません。
ただ、本コンクールの本来の意義であった、歌曲に特化したコンクールという意味合いから、課題曲にオペラのアリアを入れて審査をすべきであった、という思いも芽生えました。
元来ドイツ歌曲はドイツ発声法、フランス歌曲はフランス発声法で演奏されるべきです。しかしながら現代の歌手の場合、レパートリーにオペラのアリアがあることから、ベルカント唱法に統一され、その発声法で歌曲を歌うことがほとんどです。しかし歌曲は、その発声法により楽曲が生きてくるものでもあります。今回、歌曲とオペラのアリアで発声法を変えることができるかどうかを見極めることができなかったため、歌曲コンクールというより、声楽のコンクールに近いものになったことは否めません。次回は、アリアを含めて発声法を変えられるかどうかのポイントについても、審査対象としたいと考えております。
日本歌曲は、世界に誇れる美しい珠玉の楽曲揃いです。日本の歌曲もその楽曲に合った唱法で、永遠に歌い続けられるよう、本コンクールでその世界をアピールしていきたいと考えております。